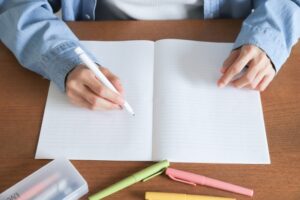高認(高等学校卒業程度認定試験)に合格すれば、「高卒」として扱ってもらえるのか。
特に就職活動の際に「高卒以上」を条件とする求人に応募できるのか、履歴書にはどう書けばいいのか、そして企業側はどう評価しているのか。
これは高認試験を受験する多くの人が気になる疑問です。進学だけでなく、就職や転職の際にも「学歴」は履歴書に記載される重要な項目です。
本記事では、高認と高卒の制度的な違いから、実際の応募時の対応、企業が求職者をどう見ているのかまでを、就活市場の視点からわかりやすく解説します。
高認は「高卒」と同じ?制度上の違いと就活市場での扱い
先に結論:高卒ではないが、多くの場合“高卒以上”の求人に応募できます。
これを説明するために、まず、「最終学歴」という言葉の定義について解説していきます。
最終学歴とは?
まず、最終学歴という言葉の定義について解説します。
最終学歴とは、「その人が卒業した学校の中で、最も水準が高い教育機関」を指します。
極端な話、ものすごく偏差値が高い大学(例えば東京大学)へ入学しても、卒業せずに中退した場合、その人は高卒として扱われることにとなります。
それと同じで、高認試験の合格者は高校を卒業したわけではないので、最終学歴を聞かれた場合は中卒と答えることになります。
ではなぜ、「高卒以上」の募集に応募できるのか
高認試験を主催する文部科学省は、高認合格者について、公式ホームページや一般企業向けパンフレットなどで以下のように触れています。
高等学校卒業程度認定試験は、学校教育法第90条第1項の規定により(中略)高校卒業者と同等以上の学力があることを認定する試験である。(中略)
引用元(2025年5月13日時点):高等学校卒業程度認定試験の概要
また、就職・資格試験等においても高校卒業者と同等に扱われるよう、経済界等に働きかけ、社会的通用性を高めるよう努めている。
採用試験における高卒認定試験(大検)合格者の扱い(文部科学省の調査)
また、文科省が行った調査によると、採用にあたって高認試験合格者を高卒と認めないと答えた企業はごく少数であるということがわかります。
| 企業 | 自治体 | |
|---|---|---|
| 高卒と同等である | 32.8% | 38.4% |
| 高卒として認めていない | 0.6% | 2.3% |
| 学歴で差はつけていない | 6.7% | 19.3% |
| 高卒認定試験の合格者が受けに来たことがなく、決めていない | 53.0% | 35.4% |
| わからない | 3.1% | 1.4% |
| その他/無記入 | 3.8% | 3.1% |
引用元:令和5年度調査結果
つまり?
文部科学省としては、高認合格者が高卒と同様に扱われるように働きかけており、企業や自治体側も、ほとんどの場合は中卒扱いをしていないということです。
絶対に高卒として扱わなければいけない、という法的な強制力があるわけではありませんが、少し安心できますね。
とはいえ「だからと言って採用されるか否かは話が別」と思うかもしれません。
それについては、次のようなデータもあります。
「高卒認定試験(大検)合格者を採用するのに不安な点がある」という意見についてどう思うか。(文部科学省調査)
| 企業 | 自治体 | |
|---|---|---|
| そう思う | 3.8% | 0.5% |
| どちらかといえばそう思う | 11.5% | 5.4% |
| どちらともいえない | 45.9% | 53.1% |
| どちらかといえばそう思わない | 17.2% | 12.9% |
| そう思わない | 21.4% | 28.0% |
| 無記入 | 0.1% | 0.1% |
引用元:令和5年度調査結果
こちらも、「高認だからといって」採用するのに不安があると考えている企業や自治体の方が少数派であるということがわかりますね。
まとめ
以上の通り、高認試験の主催である文科省は、高認合格者が採用市場において高卒と同様に扱われるように働きかけており、企業や自治体側も「高卒と認めない」「中卒として扱う」ケースが少数であることがわかります。
また求人サイトなどでも、プロフィール欄やWEB履歴書などの仕組みに、「高卒相当」などの選択肢を設けている場合があります。
「最終学歴」の記入を求められた場合は「中卒」と書かなければいけないことには注意ですが、メッセージ欄やコメント欄などがあれば、高認試験の合格者であることをアピールすることで補足ができるでしょう。