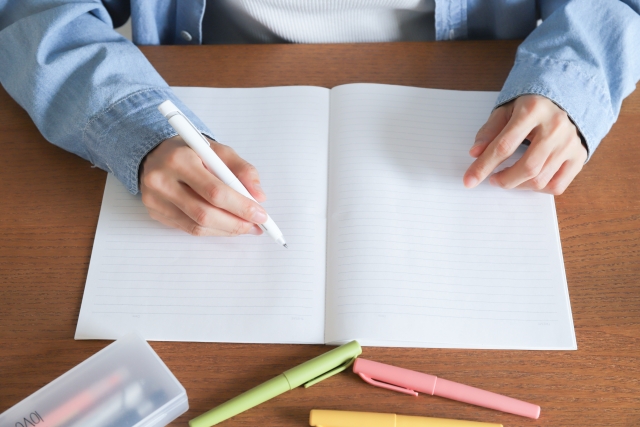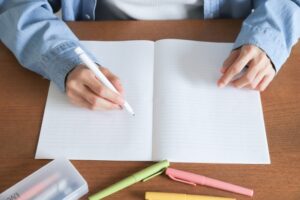高校卒業「程度」って、どのていど? 具体的にどこまで勉強すればいいの?
どのくらいの学力が必要? 普通の高校3年分の勉強を一気に覚えなければいけない?
高等学校卒業程度認定試験とは、高校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。
と言われても、何をどこまで勉強すればいいのかわかりませんよね。
特に近年は出題範囲の変更や新しい科目の追加などが相次いでおり、初めて受験する方はもちろん、一度勉強から遠ざかってしまった方にとってはピンとこないと思います。
この記事では、そんな疑問にお答えし、どこからどこまでを勉強すれば安心できるのか、具体的に解説します。
高認試験の出題範囲は何年生まで?
先に結論:目安としては1年生〜2年生が習う範囲。ただし、厳密には「何年生の範囲」とは言えないので、勉強する際には注意が必要。
いきなりふわっとした結論になってしまいましたね。
ご安心ください、キチンと具体的に解説していきます。
出題範囲は“科目”単位で決まっている。
たとえば高校で「国語」の授業をする場合、「現代の国語」、「言語文化」、「倫理国語」、「文学国語」……などなど、さまざまな科目に分かれています。
そして、どの科目を何年生で習うのかは、大まかにきまっているものの、学校ごとに異なるのです。
そのため、厳密には「出題範囲=何年生までの範囲」と言い切ることができないのです。
「でも、要は高校1年生〜2年生の範囲で勉強すればいいってことでしょ?」
と、思うかもしれません。しかし、出題範囲が科目で決まっているということを意識するだけで、勉強のやり方がだいぶ変わってきます。
このことについて、後ほど解説していきます。
過去問や問題集が当てにならないことがある
数年前までの高認試験は出題範囲がパターン化されており、過去問や参考書をやりこむだけで、ある程度の点数を取れるようになっていました。
しかし近年、出題範囲の変更や新しい科目の追加が相次いでいます。
その影響で、参考書を作る会社にも出題傾向のデータが蓄積されていないのか、出題範囲の予想が大きく外れていたという声がSNSなどで多くみられます。
この記事を書いている私も、某人気ワークブックと過去問を参考に勉強をしていましたが、多くの科目で出題範囲や出題形式が異なっていたという経験をしました。とくに英語と数学が範囲・形式ともに大きく外れており、試験会場で「初めて見る問題なんだが???」と軽く混乱してしまいました(笑)
幸い、試験には合格できましたが、少々点数を落としてしまいました。
そして、高認試験にも合格成績という概念があります。一般入試をする場合は関係がないとされているようですが、推薦入試や選抜型入試など、一部のケースでは合格成績が評価される場合もあるようです。
また、一部の審査が必要な奨学金は、学業の成績を審査基準としています。進学や留学にあたって奨学金制度の利用を検討している方は、好成績で合格することを心がけた方が良いでしょう。
具体的な出題範囲は?
以下の表に、文部科学省が定義している出題範囲の科目をまとめました。
例えば国語であれば、「現代の国語」と「言語文化」の教科書の範囲から出題される、という意味になりますね。
| 試験科目 | 出題範囲 |
|---|---|
| 国語 | 「現代の国語」「言語文化」※古文・漢文を含む |
| 地理 | 「地理総合」 |
| 歴史 | 「歴史総合」 |
| 公共 | 「公共」 |
| 数学 | 「数学Ⅰ」 |
| 科学と人間生活 | 「科学と人間生活」 |
| 物理基礎 | 「物理基礎」 |
| 化学基礎 | 「化学基礎」 |
| 生物基礎 | 「生物基礎」 |
| 地学基礎 | 「地学基礎」 |
| 英語 | 「英語コミュニケーションⅠ」 |
引用(2025年5月17日時点):高等学校卒業程度認定試験 試験科目・合格要件・出題範囲 (PDF)
実際に勉強するにあたって
出題される範囲は分かりましたね。
これをもとに実際に勉強をしていくことになりますが、範囲全てを丸暗記することは非効率です。
かといって、参考書を作る会社も予想を外すことがありますので、高得点を狙いたい場合、あるいは苦手科目の点数を少しでも上げたい場合は、教科書を入手して流し読みをすることをオススメします。
ポイントとして、全てを覚える必要はありません。流し読みをして「とりあえず全部読んだ」「〇〇という言葉について、なんとなく覚えた」というレベルで構いません。そうすれば試験会場で「初めて見る言葉が出題された!」と慌てることはなくなります。
さらに言えば、狭い範囲を完璧に仕上げるよりも、広い範囲を大まかに把握した方が勉強の効率は格段に上がります。
例えば、歴史の流れを知らずに年号を正確に暗記するのは難しいですが、
というように、ざっくりの流れと要所の年号だけ押さえておけば、「廃藩置県は1868年より後だな」とか、「戊辰戦争は、大政奉還と明治維新の間に起こったはずだな」と予想ができるようになるはずです。丸暗記よりは簡単ですね。
高認試験はマークシート方式で出題されますので、細かく正確な暗記よりも、全体の流れを理解する方が有利です。
また、この勉強方法は高認試験に限らず、今後の人生で何か他の勉強をする際にも役立つやり方ですので、他の機会があればぜひ試してみてください。
まとめ
- 高校卒業程度認定試験の出題範囲は、目安としては高校1年生〜2年生と同じくらいの範囲に相当する。
- 厳密には、何年生という範囲ではなく“科目”で範囲が決まっている。
- 出題範囲を正確に把握することで、高得点や苦手科目の点数アップを狙うことができる。
まとめると、こういった整理になります。すこしでも参考になれば幸いです。
皆さんが試験に無事、合格されることを応援しています。